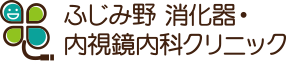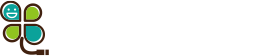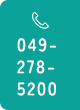骨粗しょう症とは
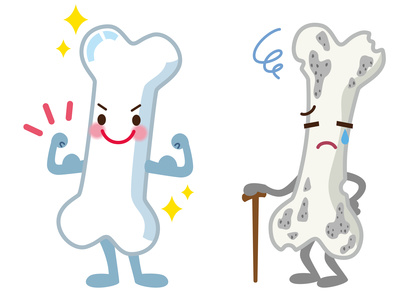 骨粗しょう症(こつそしょう症)とは、加齢により、骨がもろくなる(骨密度が低下する)病気のことです。骨粗しょう症の状態になると、転倒などをきっかけに容易に骨折をしやすくなります。人によっては無自覚のまま骨折していることもあります(以前より身長が縮んできた等)。また骨折は寝たきりの主な原因の一つであり、介護と密接に関わっています。骨折をしてから骨粗しょう症だったことを初めて知る患者さんやそのご家族は多いです。加齢は抗えませんが、できる限り骨折しにくい状況を作っておくこと、すなわち健康な骨の維持に努めることは非常に大切です。
骨粗しょう症(こつそしょう症)とは、加齢により、骨がもろくなる(骨密度が低下する)病気のことです。骨粗しょう症の状態になると、転倒などをきっかけに容易に骨折をしやすくなります。人によっては無自覚のまま骨折していることもあります(以前より身長が縮んできた等)。また骨折は寝たきりの主な原因の一つであり、介護と密接に関わっています。骨折をしてから骨粗しょう症だったことを初めて知る患者さんやそのご家族は多いです。加齢は抗えませんが、できる限り骨折しにくい状況を作っておくこと、すなわち健康な骨の維持に努めることは非常に大切です。
骨折前の段階では骨粗しょう症の自覚症状は乏しいことも多いため、重要なことは、自分が骨粗しょう症になっているかどうかを年齢の節目ごとに検査で把握し、治療で予防することです。加齢以外では、女性ホルモンの低下と関連が深いため、特に40代以降の女性は5年に一度程度の定期的な骨密度検査をお勧めします(50歳以上は男性もお勧めします)。骨粗しょう症の治療目標は、骨密度の低下を抑え、骨折をできる限り予防することです。そのため、普段における生活習慣の見直し、一人一人のコンディションに合わせた適度な運動による筋力維持、そして検査で骨密度が低下している方には適切な薬物治療によって骨密度の低下を抑制すること、これらをうまく組み合わせ、健康な骨の維持を目指しましょう。
骨粗しょう症にはどんな症状がありますか?
骨粗しょう症になっても、多くの場合は痛みを感じません。しかし、転倒などのちょっとした衝撃で骨折しやすくなります。骨折しやすい部位には、背骨(脊椎圧迫骨折)、手首(橈骨遠位端骨折)、太ももの付け根(大腿骨頚部骨折)などがあります。
骨折が起こると、痛みのためにその部位が動かせなくなることがあります。また、背中や腰の痛みの後に、背中が丸くなったり、身長が縮んだりすることもあります。
- 以前より身長が低くなった
- 背中や腰が曲がってきた
- 背中や腰に痛みがある
このような症状のうち、ひとつでも当てはまる場合は骨粗しょう症の可能性があります。早めの検査をおすすめします。
骨粗しょう症の原因
私たちの骨は、日々「壊す(骨吸収)」と「作る(骨形成)」というサイクルを繰り返しながら生まれ変わっています。健康で丈夫な骨を保つためには、この骨吸収と骨形成のバランスが適切に保たれていることが重要です。
しかし、このバランスが崩れると、質の低い脆い骨が作られるようになり、これが骨粗しょう症の原因となります。骨粗しょう症の主な要因には、次のようなものがあります。
加齢による骨代謝の低下
年齢を重ねるにつれて、新しい骨をつくる骨芽細胞の働きが衰えてきます。その結果、骨を壊すスピード(骨吸収)が骨を作るスピード(骨形成)を上回り、骨の強度が低下してしまいます。
女性ホルモンの減少
女性ホルモン(エストロゲン)には、骨の形成を促し、骨の吸収を抑える働きがあります。しかし、更年期に入り閉経を迎えるとエストロゲンが急激に減少し、その結果として骨密度が急速に低下します。これにより、わずかな衝撃でも骨折しやすい状態になります。
病気や生活習慣、家族歴の影響
骨粗しょう症は、以下のような疾患の影響でも引き起こされることがあります。
- 糖尿病
- 動脈硬化
- 甲状腺機能亢進症
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 関節リウマチ など
また、家族歴がある方(両親のいずれかが大腿骨頸部骨折になっている)、偏った食生活・運動不足、喫煙、飲酒などの生活習慣も、骨に悪影響を与える要因となります。
骨粗しょう症検診のすすめ
 骨密度が低下し始める40歳以上の女性は5年毎で受けていただくとよいでしょう。男性が生じる割合は女性の1/3程度と言われていますが、男性も加齢とともに骨粗しょう症になります。男性も目安として50歳以降は定期的な骨密度検査をおすすめします。
骨密度が低下し始める40歳以上の女性は5年毎で受けていただくとよいでしょう。男性が生じる割合は女性の1/3程度と言われていますが、男性も加齢とともに骨粗しょう症になります。男性も目安として50歳以降は定期的な骨密度検査をおすすめします。
骨粗しょう症は自覚症状に乏しいため、骨折してから骨粗しょう症になっていたことが判明することもあります。 従って、骨粗しょう症が進行する前から早期の予防や治療が受けられるように、40歳以上になったら骨粗しょう症検診を積極的に活用するとよいでしょう。
骨粗しょう症の検査法(DIP法)
 骨量測定にはいくつかの種類があります。腰椎(背骨)や大腿骨近位部(足のつけ根)といった骨折が起こりやすい部位の骨密度をデキサ法(DXA)で測定するのが最も正確な評価法ですが、大型装置を必要とするため、どの医療機関でも受けられる検査ではありません。
骨量測定にはいくつかの種類があります。腰椎(背骨)や大腿骨近位部(足のつけ根)といった骨折が起こりやすい部位の骨密度をデキサ法(DXA)で測定するのが最も正確な評価法ですが、大型装置を必要とするため、どの医療機関でも受けられる検査ではありません。
当院では、骨塩定量測定にDIP法を採用しています。DIP法は、手のひらをレントゲン撮影し、人さし指の骨とアルミニウムの濃度を比較して骨密度を測定する検査方法です。被ばく線量が少なく、簡便に測定できるため、骨粗しょう症のスクリーニングに適しています。検査の結果、骨粗しょう症が明らかであれば治療を開始します。スクリーニングでは明らかな異常がみられないものの、さらなる精査が必要な場合はデキサ法(DXA)が実施できる専門の医療機関をご紹介させていただきます。
骨粗しょう症の診断基準
骨粗しょう症の診断は、問診と骨密度の測定結果を組み合わせて行います。特に、脆弱性骨折(大腿骨近位部骨折や椎体骨折など)の有無は、骨粗しょう症の診断および治療方針の決定において重要な要素となります。
YAM(Young Adult Mean)とは「若年成人平均値」の意味の事で、20~44歳までの健康女性の骨密度の平均値がYAM値として用いられます。骨密度測定検査では、この基準となるYAMを指標として、「現在の骨量はどの程度あるのか?」を数値としてデータ化し、現状の骨密度の状況を確認していきます。
I.脆弱性骨折あり
- 椎体骨折または大腿骨近位部骨折
- その他の脆弱性骨折で骨密度がYAMの80%未満
II.脆弱性骨折なし
- 骨密度がYAMの70%以下または-2.5SD以下
III.骨量減少(YAM 70%より大きく80%未満)
- 喫煙歴、アルコール3単位/日以上、両親の大腿骨近位部骨折の家族歴がある場合などは治療を考慮 ※アルコール約1単位の目安:ビール1缶、ワイングラス1杯
骨粗しょう症の治療法
骨粗しょう症の薬には大きく分けて3つのタイプがあります。
骨吸収抑制
骨を壊す働きを抑える薬
骨形成促進
骨をつくる働きを高める薬
骨代謝調整
骨のつくり替えのバランスを整える薬
| 主な薬の種類 | 骨吸収抑制 | 骨形成促進 | 骨代謝調整 |
|---|---|---|---|
| ビスホスホネート薬 | 〇 | ||
| 選択的エストロゲン受容体作用薬(サーム) | 〇 | ||
| 活性型ビタミンD3薬 | 〇 | ||
| ビタミンK2薬 | 〇 | ||
| 抗ランクル抗体薬(注射のみ) | 〇 | ||
| 副甲状腺ホルモン薬(注射のみ) | 〇 |
骨粗しょう症の治療の基本は、内服薬になります。骨折リスクが高い場合や内服治療が難しい場合は注射による治療を考慮することもあります。健康寿命を保つことが主な目標ですので、薬を始めたら一生飲み続けなければいけないということではありません。ただし、治療を止めてしまうと骨粗しょう症は進行しますので、無理なくできる限り長く治療を継続していくことが長期的な予防の視点からは大切になります。骨粗しょう症の程度や治療を受ける年代、性別、生活パターン等を考慮しつつ、また内服薬の種類によっても服用方法の違いがあるため、患者さん一人一人に合った最適な治療を行います。
骨粗しょう症の予防
骨粗しょう症の予防には、加齢や閉経、遺伝的要因だけでなく、日々の生活習慣が大きく関わっています。骨の健康を維持するためには、バランスの良い食事と適度な運動が欠かせません。このため、骨粗しょう症は「骨の生活習慣病」とも呼ばれており、生活習慣の見直しが予防や治療において非常に重要です。
具体的には、カルシウムやビタミンD、ビタミンKを十分に摂ること、体内のビタミンDを活性化する適度な日光浴、ウォーキングや筋力トレーニングなどの適度な運動を続けることが効果的です。また、喫煙やアルコールの摂り過ぎは控えた方がよいでしょう。
骨粗しょう症のよくある質問
骨粗しょう症になる人の特徴は?
骨粗しょう症のリスクが高い方には、以下のような特徴があります。
- 閉経後の女性
- 60歳以上の男性
- 軽い転倒や衝撃で骨折をしたことがある方
- 関節リウマチ、糖尿病、慢性腎臓病、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの持病がある方
- ステロイド薬を長期間使用している方
- 喫煙習慣のある方、または日常的に多量の飲酒をされる方
- ご家族に股関節骨折(大腿骨近位部骨折)の既往がある方
これらに該当する方は、骨粗しょう症のリスクが高いため、定期的な骨密度検査をおすすめします。
骨粗しょう症の骨密度は回復しますか?
骨粗しょう症による骨密度の低下を完全に元の状態に戻すことは難しいですが、治療を通じて現状を維持したり改善したりすることは可能です。特に、早期発見と適切な治療、そして生活習慣の見直しを継続することが大切です。
骨密度が70パーセント以下だとどうなりますか?
骨密度が70%以下で、骨粗しょう症と診断し、治療が推奨されます。骨粗しょう症は骨がもろくなる病気で、わずかな衝撃でも骨折しやすくなる特徴があり、将来の骨折リスクが高くなります。
骨密度を上げる食べ物は?
骨密度を上げるためには、カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、タンパク質を豊富に含む食品を積極的に摂取することが重要です。特に、牛乳や乳製品、小魚、緑黄色野菜、大豆製品、魚介類などがおすすめです。
骨密度を上げるための具体的な食品
- カルシウム:牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、小魚(しらす、煮干しなど)、豆腐、納豆、ひじき、小松菜、チンゲン菜など
- ビタミンD:鮭、うなぎ、干し椎茸、キクラゲ、卵など
- ビタミンK:納豆、モロヘイヤ、ほうれん草、春菊など
- タンパク質:肉、魚、卵、大豆製品、乳製品など
骨粗しょう症は治るのですか?
骨粗しょう症は完治が難しい病気ですが、適切な治療と生活習慣の見直しを行うことで、骨折のリスクを低減し、病気の進行を抑えることが可能です。薬物療法に加え、運動や食事療法を組み合わせることで骨密度を改善し、日常生活の質を高めることができます。