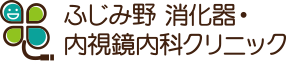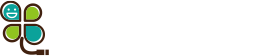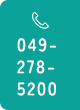高血圧症
 日本人の4人に1人、特に60歳以上の約半数は高血圧症に罹患していると考えられています。昔から日本は脳卒中(特に脳出血)が非常に多いことで知られていますが、この主な原因が高血圧症です。降圧薬の普及に伴い、以前より脳出血を発症する人は減少していますが、それでもいまだに脳出血は多いですし、脳卒中の中でも脳梗塞は非常に多くみられる病気の一つです。高血圧症そのものに自覚症状はありません。健診で血圧異常を指摘されることが受診のきっかけになるケースがほとんどです。
日本人の4人に1人、特に60歳以上の約半数は高血圧症に罹患していると考えられています。昔から日本は脳卒中(特に脳出血)が非常に多いことで知られていますが、この主な原因が高血圧症です。降圧薬の普及に伴い、以前より脳出血を発症する人は減少していますが、それでもいまだに脳出血は多いですし、脳卒中の中でも脳梗塞は非常に多くみられる病気の一つです。高血圧症そのものに自覚症状はありません。健診で血圧異常を指摘されることが受診のきっかけになるケースがほとんどです。
高血圧症の原因
高血圧の患者さんの約95%は加齢や遺伝的な要因に加え、塩分過多、ストレス、肥満、喫煙などの生活習慣の乱れ、睡眠時無呼吸症候群などが影響しています。
減塩(薄味)を意識した食生活、肥満がある方は減量、喫煙習慣がある方は禁煙することで、血圧は改善します。睡眠時無呼吸症候群は高血圧症との関連が高く治療で改善しますので、イビキや日中の眠気などの症状がある方はお気軽にご相談ください。
高血圧の基準値
日本高血圧学会のガイドラインによる高血圧の治療を開始する血圧の基準値
診察室血圧で140/90㎜Hg、家庭血圧で135/85㎜Hg
日本高血圧学会のガイドラインによる降圧目標値
75歳未満の成人 130/80㎜Hg未満(家庭血圧125/75㎜Hg未満)
糖尿病合併 130/80㎜Hg未満(家庭血圧125/75㎜Hg未満)
慢性腎臓病(蛋白尿陽性) 130/80㎜Hg未満(家庭血圧125/75㎜Hg未満)
75歳以上 140/90㎜Hg未満(家庭血圧135/85㎜Hg未満)
※血圧は運動や緊張、環境の変化など、さまざまなことから影響を受けて変化するものです。血圧を計測する際、病院やクリニックでは緊張して高めで、リラックスできるご自宅では低めの傾向があるため、診察時の血圧と家庭血圧は別の数値になっています。
家庭血圧の重要性
 適切な血圧測定法として、自宅で毎日朝起きた時と寝る前の1日2回(1日1回朝起きた時のみも可)座ってリラックスした状態で行うことを推奨しています。血圧測定前は先にトイレを済ませておきましょう。日中に外出先で測定したり、外来で測定したりすると血圧の値が家庭血圧の時よりも高くなる人がしばしばみられます。日中の活動中は一般に血圧は高くなりやすいことや、精神的に緊張すると高くなりやすくなります。
適切な血圧測定法として、自宅で毎日朝起きた時と寝る前の1日2回(1日1回朝起きた時のみも可)座ってリラックスした状態で行うことを推奨しています。血圧測定前は先にトイレを済ませておきましょう。日中に外出先で測定したり、外来で測定したりすると血圧の値が家庭血圧の時よりも高くなる人がしばしばみられます。日中の活動中は一般に血圧は高くなりやすいことや、精神的に緊張すると高くなりやすくなります。
降圧薬による治療を行う際、1日の中で最も低い血圧である家庭血圧を目安にします。なぜなら日中の高い値のみを指標にしてしまうと、1日で最も低い値が治療によりさらに低くなり、低血圧になってしまう危険性があるからです。あくまで降圧目標は1日の平均的な血圧の値が低くなることです。ですから家庭血圧の把握は非常に大切です。
高血圧症の合併症
高血圧症は、長く放置しておくと、脳出血、脳梗塞、認知症、狭心症/心筋梗塞、慢性腎臓病→末期腎不全(人工透析を要する)、パーキンソン症候群、大動脈瘤破裂、大動脈解離などの合併症を引き起こす原因となります。
高血圧症の診断
健診で血圧高値を指摘されたら、まず家庭血圧計で起床時と寝る前の血圧を毎日測定します。健診や日中の血圧の値は、緊張や活動による血圧上昇だけを見ている場合があるため、正確な評価は安静時の状態で測定する一定期間の血圧の平均値で行います。
血圧の値は毎回測定するたびに変化します。体調によっては普段より高いとき、あるいは低いときもあるでしょう。高血圧による合併症をできる限り回避するために、平均血圧を適切な値まで下げておくことが大切です。
高血圧の治療
降圧薬(血圧を下げるための薬)の内服治療が基本となります。服用方法は1日1回です。生活習慣の乱れがある場合は軌道修正も行いましょう。(当てはまる方は)薄味、禁煙、体重の減量がポイントです。
降圧剤(血圧を下げるための薬)には様々な種類がありますが、患者さんにあったお薬をガイドラインに準じ、原則として1種類のお薬を少量から開始します。急激に強い治療を行ってしまうと、体が適応できなくなり、体の負担が大きくなってしまうからです。その後は血圧の値をみながら、お薬を増量したり、種類を追加したりして、徐々に降圧目標の血圧値へコントロールしていきます。
降圧薬は1~2種類で血圧コントロール可能な場合が多いです。肥満や喫煙習慣のある方は血圧コントロールが不十分になりやすく、3~4種類の降圧薬が必要になる場合もあります。
治療継続の重要性
 健康寿命を保つことが主な目標ですので、薬を始めたら一生飲み続けなければいけないということではありません。しかし、治療を止めてしまうと血圧は再び上昇しますので、無理なくできる限り長く治療を継続していくことが長期的な予防の視点からは大切になります。
健康寿命を保つことが主な目標ですので、薬を始めたら一生飲み続けなければいけないということではありません。しかし、治療を止めてしまうと血圧は再び上昇しますので、無理なくできる限り長く治療を継続していくことが長期的な予防の視点からは大切になります。
<降圧薬を服用する際の注意点>
毎日の家庭血圧の値をみて、今日は調子が良いからと自己判断で服用したり止めたりすることは絶対に止めてください。血圧の大きな変動は血管に過剰な負担がかかり危険です。毎日服用を継続し、平均血圧が基準内におさまるように、医師と相談しながら治療を継続していきましょう。
気温が上がる夏場は発汗による塩分の喪失や脱水も生じやすい時期です。一年を通して夏の時期は血圧もやや低めで推移することが多い季節ですので、血圧の下がりすぎには注意が必要です。具体的には収縮期血圧が100mmHgを下回るようなら、医師に相談し、降圧薬の減量を検討してもらいましょう。