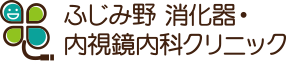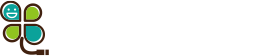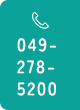生活習慣病とは
 生活習慣病とは、暴飲暴食、喫煙、ストレス、運動不足など不摂生な生活を続けることで発症する病気の総称のことです。最近では、新型コロナウイルスの影響によって自宅で過ごされる時間が多くなり、高齢者だけでなく若い方でも生活習慣が乱れてしまい、生活習慣病となってしまう方が増えてきています。
生活習慣病とは、暴飲暴食、喫煙、ストレス、運動不足など不摂生な生活を続けることで発症する病気の総称のことです。最近では、新型コロナウイルスの影響によって自宅で過ごされる時間が多くなり、高齢者だけでなく若い方でも生活習慣が乱れてしまい、生活習慣病となってしまう方が増えてきています。
当院では、患者さんに以下のような内容を伺い、生活習慣の改善をサポートできるようにしております。
- 1日の食事回数、食事の内容
- 飲酒や喫煙の量、回数
- 1日の睡眠時間、床に就く時間
- ストレスのコントロール
- 1日の運動時間や種類
高血圧症
日本人の4人に1人、特に60歳以上の約半数は高血圧症に罹患していると考えられています。昔から日本は脳卒中(特に脳出血)が非常に多いことで知られていますが、この主な原因が高血圧症です。降圧薬の普及に伴い、以前より脳出血を発症する人は減少していますが、それでもいまだに脳出血は多いですし、脳卒中の中でも脳梗塞は非常に多くみられる病気の一つです。高血圧症そのものに自覚症状はありません。健診で血圧異常を指摘されることが受診のきっかけになるケースがほとんどです。
脂質異常症(高脂血症)
脂質異常症とは、血液中の脂質の値が基準値を超えた状態となってしまっている病気のことを言います。脂質は主にコレステロールと中性脂肪に分けられ、栄養学的には、人にとって必須の栄養素の一つで、体の細胞を構成する成分や、エネルギー源としても重要ですが、体内で過剰に存在すると様々な病気を引き起こします。
一般的には高脂肪食が原因で生じる病気であり、心当たりのある方はまず食事を中心とした生活習慣の改善を行うことは言うまでもありません。しかし重要なことで一般にあまり知られてはいませんが、脂質異常症は遺伝的な要素が非常に大きい病気の一つです。つまり、祖父母、父母、兄弟で脂質異常症の方がいる場合、特に食生活が乱れていなくても、小太り・肥満などではなくても、20歳代、30歳代と若い方で痩せている方でも著明に高値を示す脂質異常症が見つかるケースがしばしば見受けられます。こうしたケースでよくあるのが、検診で異常を指摘されたが、恥ずかしくて相談しづらい(特に女性に多い)、若いから自分は大丈夫、生活習慣は乱れていないから自分は大丈夫と思い込み放置されてしまっている場合です。
脂質異常症を放置すると、動脈硬化といって血管が固くなり、血管の内側に油の汚れが付着して血管がもろくなったり血管が細くなったりして、急性心筋梗塞や脳梗塞をきたしたり、加齢とともに認知症にもつながっていきます。脂質異常症は原則として1種類の飲み薬を毎日服用するだけで正常値にコントロールできる病気です。自覚症状がないため、治療を行う動機付けが得られにくい病気の一つですが、将来の健康維持のための自己投資だと思って頂くとよいかもしれません。
脂質異常の基準値
高LDL(悪玉)コレステロール血症 ≧140mg/dl(120~139 mg/dlは境界域)
低HDL(善玉)コレステロール血症 <40 mg/dl
高トリグリセライド(中性脂肪)血症 ≧150 mg/dl
脂質異常症の治療
治療
基本的には、食事療法と運動療法によって生活習慣の見直しを行い、症状の改善を図っていきます。なお、脂質異常症にはいくつかタイプがあり、細かい治療方針は症状によって異なるため、以下を参考にしてください。
高LDLコレステロール血症
血液中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が多い状態のことを言います。食事療法において、1日の摂取カロリー(エネルギー)を適正値に保つこととバランスよく1日3食の食事を取ることが大切となります。なお、コレステロールが高い卵や脂質の多い肉類の多量の摂取は控え、活性酸素を除去する野菜やフルーツ、EPA・DHAが豊富な青魚、食物繊維が豊富なキノコや豆類など、栄養バランスの良い食事を心がけていきましょう。
高トリグリセライド血症
トリグリセライドとは、肉、魚、油など、食べ物に含まれる脂質や体脂肪の大部分を占める物質のことで、中性脂肪と呼ばれることもあります。血中のトリグリセライドの値を下げるためには、1日3食の規則正しい栄養バランスの良い食生活、1日30分以上の運動を週3日程度行うことが大切です。なお、栄養バランスが整っているからといって食べ過ぎは禁物で、腹8分目程度で抑えるようにするとよいでしょう。
低HDLコレステロール血症
善玉コレステロールの値が低い状態です。食事では、マーガリンやショートニングなどトランス脂肪酸の取り過ぎは禁物ですが、極端な脂質制限とならないようバランスの良い食生活を心がけるようにしましょう。
脂質異常症の治療薬
軽症高値の場合や生活習慣の乱れがある方は、まず食事療法と運動療法による生活習慣の是正を行っていただき改善をはかります。それでも改善が乏しい場合に薬物療法を行います。一方、発見された当初から値が高かったり、遺伝性が高いと考えられたりする場合は最初から薬物治療を行います。一つ注意点としては、お薬の治療は毎日服用しないと適切なよい状態を保てないということです。お薬を飲んでいない間は効果が得られませんので、頻繁に飲み忘れたり自己中断したりしてしまうと、元の高い値に逆戻りしてしまいますのでご注意ください。
糖尿病
糖尿病とは、血液中のブドウ糖の量(血糖値)が増え過ぎる結果、全身の血管にダメージを与えてしまう病気のことです。通常は膵臓で分泌されるインスリンというホルモンが血糖値を適切にコントロールしていますが、糖尿病になると、インスリンでコントロールできないレベルまで血糖値が上昇します。糖尿病の初期段階では自覚症状が乏しいため、通常診断は血液検査を用いて行い、血糖値とHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)値という項目で評価します。HbA1c値は過去2か月間における血糖の推移の平均をみていますので、診断時と治療後の改善の程度を評価する指標としても用いられます。糖尿病の病名からは尿に甘い糖が出るというイメージを持たれている方が多いかもしれませんが、尿の検査のみでは診断できません。健康診断や人間ドックなどで糖尿病の値の異常を指摘されたら、お気軽にご相談ください。なお、自覚症状が現れる頃には病状が悪化してからのことが多いため、喉の異常な渇き、疲れやすい、多尿、体重減少などの症状が現れた場合はお早めにご相談ください。
高尿酸血症(痛風)
高尿酸血症自体は無症状ですが、血中濃度が8㎎/dlを超える状態が続くと、痛風発作や腎結石、尿路尿管結石、腎機能障害(痛風腎)を引き起こしたり、尿酸の結晶が耳介や足の親指、肘関節などに結節の形(痛風結節)で出現したりすることがあります。男女比は10:1と男性にとても多い病気です。血液中の尿酸の元はプリン体と呼ばれる成分で、8割は体内で生成され、残りの2割は食事から摂取していると言われています。治療はプリン体を多く含む食品を避けることと、尿酸値を下げる飲み薬の服用を行うことです。
痛風発作について
痛風発作とは、血中尿酸値が高い状態が続いて関節の中で尿酸の結晶が生じ、炎症を起こした状態のことです。典型的には足の親指の付け根が赤く腫れあがり激痛を生じます。非典型例で足首、足の甲、膝、手首に発作が起こることもあります。特に夏場の暑い時期に脱水状態となった際に生じやすいため、適度な水分摂取は予防として大切です。治療は消炎鎮痛薬を服用して腫れと痛みが改善するまで行います。症状が落ち着いたところで、今後の再発予防に尿酸値を下げる飲み薬の服用を行います。
プリン体を多く含む食品とお酒
一般的には肉類や魚介類を多く摂り、飲酒習慣があるとプリン体摂取量が多くなりやすいとされています。具体的には、レバー、白子、エビ、イワシ、カツオ、干椎茸や魚の干物などが挙げられます。昨今は健康食品ブームと言われますが、DNA/RNA(核酸)、ビール酵母、クロレラ、ローヤルゼリーはプリン体が非常に多く含まれているので摂り過ぎには注意が必要かもしれません。飲酒については、一般的に日本酒・ビール・ワインなどの醸造酒よりも焼酎・ウィスキーなど蒸留酒の方がプリン体含有量は少ないとされています。飲酒習慣がある人はそうでない人よりも痛風発作に2倍なりやすいと言われていますので、適度な飲酒を心がけましょう。男性で、飲酒習慣があり、プリン体を多く含む食品を好む人、脱水のエピソードは痛風発作のリスクになることを覚えておきましょう。
高尿酸血症の治療
高尿酸血症の治療には、食事療法、運動療法など生活習慣の改善を行い、尿酸値を下げていくことを目指します。また、痛風発作を繰り返しているような患者さんに対しては、尿酸産生抑制薬や尿酸排泄抑制薬などを使って薬物療法も行っていきます。治療において注意すべきポイントとして、尿酸値を急激に下げてしまうと痛風発作が起こりやすくなると言われているため、特に薬の服用を始めて3カ月間は徐々に尿酸値を下げるようにコントロールしていきます。なお、生活習慣の改善や薬物療法によって尿酸値が下がり始めてから、実際に尿酸結晶が溶けるまでには数カ月~数年の時間がかかると言われているため、根気よく治療を続けていくことが大切となります。
生活習慣
特に、BMI(体重÷身長の2乗で表される肥満指数)が25以上の肥満の方は痛風のリスクが高いため、減量を目指していくことが必要です。運動療法は必ず医師に指導を受けてください。なお、しっかり水分を補給して尿の排出量を増やすことも有効ですが、心疾患や腎疾患がある方は医師の指導で適切な水分量を取る必要があります。
食事
食事療法では、1日のプリン体摂取量を400mg未満に抑えることを目指していきます。肉(レバーなどの内臓系の部位)や魚の動物たんぱくにはプリン体が多く含まれていますので、摂りすぎないように注意しましょう。また、お酒にもプリン体が多く含まれていますので、目安としてビールは500ml未満、日本酒は1合未満に控えるようにすると良いでしょう。
メタボリック
シンドローム
 メタボリックは「代謝」、シンドロームは「症候群」という意味です。そして、メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に代謝機能不全が合わさって、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか2つ以上を併せもった状態をいいます。また、メタボリックシンドロームは、高血圧・糖尿病などの生活習慣病や、高尿酸血症、腎臓病を併発する危険性が高いと言われています。さらに、メタボリックシンドロームを放置すると、急性心筋梗塞、脳梗塞などの重大な病気に繋がり、最悪の場合は命に関わる事態となる恐れもあるため、注意が必要です。そのため、食事療法、運動療法を行い、体重、血圧、血糖値などを管理していくことが必要となります。
メタボリックは「代謝」、シンドロームは「症候群」という意味です。そして、メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に代謝機能不全が合わさって、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか2つ以上を併せもった状態をいいます。また、メタボリックシンドロームは、高血圧・糖尿病などの生活習慣病や、高尿酸血症、腎臓病を併発する危険性が高いと言われています。さらに、メタボリックシンドロームを放置すると、急性心筋梗塞、脳梗塞などの重大な病気に繋がり、最悪の場合は命に関わる事態となる恐れもあるため、注意が必要です。そのため、食事療法、運動療法を行い、体重、血圧、血糖値などを管理していくことが必要となります。
メタボリックシンドロームの診断基準
必須項目
内臓脂肪型肥満かの判断ではウエスト周囲径を必須項目として測定します。立った状態で軽呼気時に行い、臍の位置で計測します。
男性 ≧85cm
女性 ≧90cm
選択項目
血圧・血糖・血中脂質の数値が、下記の2項目以上に該当しているかどうかを確認します。
収縮期(最大)血圧 ≧130mmHg
拡張期(最小)血圧 ≧85mmHg
高トリグリセライド血症 ≧150mg/dl
低HDLコレステロール血症 <40mg/dl
空腹時高血糖 ≧110mg/dl