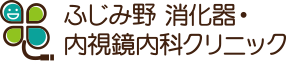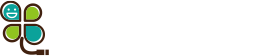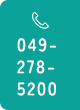萎縮性胃炎とは
 萎縮性胃炎とは、ヘリコバクター・ピロリ菌(以下、ピロリ菌)の感染によって慢性的に胃粘膜の炎症を生じ、胃粘膜が萎縮する状態のことを言います。自覚症状には個人差があり、無症状の人もいれば、様々な胃の症状を自覚する場合もあります。
萎縮性胃炎とは、ヘリコバクター・ピロリ菌(以下、ピロリ菌)の感染によって慢性的に胃粘膜の炎症を生じ、胃粘膜が萎縮する状態のことを言います。自覚症状には個人差があり、無症状の人もいれば、様々な胃の症状を自覚する場合もあります。
ピロリ菌に持続感染していると(ピロリ現感染と言います)胃潰瘍や十二指腸潰瘍になりやすいと言われています。またピロリ菌に持続感染している人(ピロリ現感染)や、ピロリ菌に過去感染していた人(ピロリ既感染)は、将来的に胃がんになりやすいことで有名です。つまり萎縮性胃炎は胃がんのリスク因子として非常に重要です。
萎縮性胃炎の症状
主な症状
- 自覚症状はありません
萎縮性胃炎には自覚症状がありません。上腹部の痛みや熱くなる感じ、胃もたれ、胃のむかつき等のいわゆる胃の症状は、萎縮性胃炎に特有の症状ではなく、ほとんど(99%以上)は「胃の調子の問題」であり病気でも何でもありません。ストレスや食事の内容などによる一過性の症状であり、症状に合わせた胃薬の服用と生活上の原因が解決することでも自然に治ります。これを機能性ディスペプシアと呼びます。胃潰瘍は胃の痛みがないことがほとんどであり、多くは出血症状を伴って発症しますので、採血で貧血を指摘されたり、どす黒い便が出たりしたことを契機に胃カメラで診断されることが多いです。胃潰瘍はピロリ菌が主な原因ですので、ピロリ菌を除菌すれば再発しません。頭痛や生理痛などに用いる解熱鎮痛薬を服用することで生じる胃潰瘍もありますので、症状を自覚する直前の鎮痛薬服用歴も重要です。胃がんは初期には自覚症状がないので自分で気づくことはできません。進行癌になると食欲低下が改善せず、体重が進行性に減少し、黒色便や吐血などの出血症状などを契機に胃カメラを受け診断されることが多いです。
萎縮性胃炎の原因
萎縮性胃炎は、幼少期にヘリコバクター・ピロリ菌(ピロリ菌)が胃の中に感染し、長期に渡り胃粘膜の持続的な炎症を引き起こすことで生じます。最初は胃の出口付近である前庭部から胃の中心である胃体部に炎症が広がっていき、炎症に伴い胃粘膜は萎縮します(そのため萎縮性胃炎と言います)。
世界的にみて、日本を含む東アジア地域ではピロリ感染者が非常に多いことが知られており、日本では中高年の方に感染者が多いです。若年者では感染者数の減少が指摘されています。いまだ正確な感染ルートは解明されていないため、若年者の感染者はいまだに一定の確率で存在しています。
萎縮性胃炎の検査
 萎縮性胃炎が疑われたら、まずは胃カメラ検査を実施します。胃カメラ検査で萎縮性胃炎と診断したら、ピロリ菌が現在感染しているかどうかを調べます。当院では院内にピロリ菌の専用検査機器(尿素呼気試験)を導入しておりますので、検査後2分で結果が判明します。
萎縮性胃炎が疑われたら、まずは胃カメラ検査を実施します。胃カメラ検査で萎縮性胃炎と診断したら、ピロリ菌が現在感染しているかどうかを調べます。当院では院内にピロリ菌の専用検査機器(尿素呼気試験)を導入しておりますので、検査後2分で結果が判明します。
ピロリ菌が陽性だった場合は除菌治療を行います。ピロリ菌が現在いなければ(自然除菌後と言います)除菌治療を行う必要はありませんが、除菌後も自然除菌後も、萎縮性胃炎があるので将来的に胃がんを発症するリスクが高いため、定期的に1~2年に1回の胃カメラ検査を行っていきます。
なお保険診療以外にピロリ菌の有無を調べる検査方法としては、当該年度で41歳になる人のみ対象の、胃がんリスク検診(ABCD検診、採血による検査)を利用することも可能です。検診で要精査と判定された方は、胃カメラ検査と、除菌治療を行います。
萎縮性胃炎の治療方法
萎縮性胃炎そのものの治療はありませんが、診断時点でピロリ菌の存在が証明された場合はピロリ除菌治療を行います。除菌成功後はピロリ菌が再感染することはありませんので、萎縮性胃炎そのものに対する継続的な治療はありません。
ピロリ除菌後(および自然除菌後)は、年1回の胃カメラ検査による定期検査を行います。理由としては、除菌後も萎縮性胃炎から胃がんが発生するリスクがあるからです。除菌によって胃がんの発がん率は多少低下させると言われていますが、発がん母地が残っている限り、胃がんの発生そのものを除菌治療だけで完全に取り除くことはできません。
胃がんは自覚症状に乏しく、年単位でゆっくり発生・進行していくため、1~2年に1回の胃カメラ検査を受けておけば、経過中に胃がんができても早期に発見し治療することができます。また定期的な胃カメラ検査によって胃がんがないことを確認できるという安心感も得ることができると思います。
胃がんは早期発見・早期治療が大切です。当院ではピロリ検査、除菌治療、1~2年に1回の定期的な胃カメラ検査全てに対応しておりますので、安心してお気軽にご相談ください。